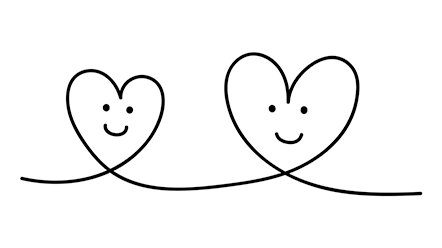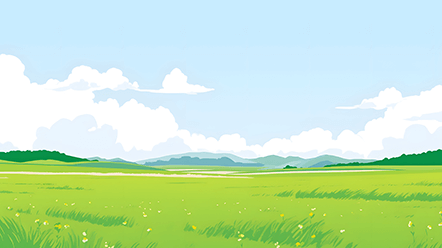研究公募情報・採択結果


- HOME
- 革新的自殺研究推進プログラム
- 研究公募情報・採択結果
- 令和7年度 革新的自殺研究推進プログラム 委託研究公募
(※受付を終了しました)
令和7年度 革新的自殺研究推進プログラム 委託研究公募
(※受付を終了しました)
1.令和7年度委託研究について
革新的自殺研究推進プログラム(以下、「本プログラム」という。)は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有することに鑑み、保健医療のみならず他部門との連携の在り方を含めた科学的根拠に基づく自殺総合対策を強力に推進するための研究プログラムです。
本プログラムの目的は、自殺対策の実践的な研究(政策研究)を通じて、自殺総合対策の推進に資するデータ及び科学的根拠を収集することにより、自殺総合対策の推進を図ることです。換言すれば、自殺対策の現場(最前線)の取り組みが研究の対象となり、研究で得られたエビデンス等が政策の根拠となって、実現された政策が自殺対策の現場の取り組みを更に後押しするような、自殺対策の「現場」と「研究」と「政策」の連動性を高めるための、革新的な自殺対策研究の推進を目的としています。
令和7年度は3つの領域を設定し、公募を行います。
2.公募概要
研究期間:令和7(2025)年度内の契約締結日〜最大3年度間(最長で令和9(2027)年度末まで)
研究費 :1課題につき年度あたり最大400万円(直接経費)
※間接経費は直接経費に対して原則として一定比率(30%)で交付
公募領域:3領域と若手研究者枠※令和7年度は合計4課題程度を採択予定
公募期間:2025年7月18日(金)〜8月15日(金)17:30まで
3.公募領域
- 領域1:こども・若者に対する支援プログラムの構築・実践
日本では、自殺が15歳から39歳の各年代における死亡原因の第1位となっています。 令和6年の児童生徒における自殺者数(確定値)は529名で、これは統計のある1980(昭和55)年以降で最多です。このように、こどもや若者の自殺の状況は極めて深刻であり、こうした状況の改善に向けた対策の推進・強化が喫緊の課題となっています。
また、こどもや若者は自殺の原因・動機が不明とされる場合や、自殺に至る兆候等が見えにくい場合も少なくありません。そのため、こどもや若者のいのちを守る上では、意識せずとも健康な状態を保つとともに、そうした行動を促す生活環境や社会環境を整備すること(0次予防的取組)等が考えられます。加えて、こどもや若者の自殺に至る背景や要因、置かれた状況等を解明するとともに、それを踏まえて必要とされる支援を構築・実践していくこと等が求められます。 これらを踏まえ、領域1では以下のような課題を想定・期待しています。
(参考)令和7年6月には、こどもの自殺対策を社会全体で取り組むことを明記した、改正自殺対策基本法が成立しました。改正法では、内閣総理大臣や文部科学大臣、厚生労働大臣が関係機関と緊密に連携して施策を推進するとされ、学校がこどもの心の健康を保つために健康診断や保健指導などを行うよう努めることや、地方公共団体が守秘義務を課したうえで学校や医療機関等と必要な情報を共有し、こどもへの対策や支援を行う協議会を設置できること等が盛り込まれています。
〈領域1課題例〉
・地方公共団体におけるこども・若者への支援事業(例:こども・若者の自殺危機対応チーム事業など)の効果測定と改良プログラムの構築・実践
・住むだけでこども・若者の心身を健康な状態に導くまちづくりや、学校・住居等の生活環境の整備につながる0次予防的取組の構築・実践
・児童生徒を対象にしたSOS の出し方に関する教育プログラムの構築・実践
・相談しない・できない/相談への抵抗感を有するこどもや若者の行動変容を促すためのプログラムの構築・実践
・こどもや若者を適切な相談・支援窓口へとつなぐためのプログラムの構築・実践
・学校段階別に見た自殺の背景課題の解明とそれを踏まえた支援プログラムの構築・実践
・保護者も含めた包括的支援の提供につなぐためのプログラムの構築・実践 など
- 領域2:自殺ハイリスク群に対する支援プログラムの構築・実践
令和4年以降、年間の自殺者数が再び減少傾向にありますが、未だに2万人超の方が自殺で亡くなっています。
自殺のハイリスク群としては、自傷や自殺未遂の経験がある人は、それらの経験がない人に比べて、のちに自殺で亡くなる可能性が高いことが知られています。令和6年の自殺者数(自殺日・住居地ベース)を見ても、2割程度の方に自殺未遂歴があることが確認されています。
そのため自傷や自殺未遂に至った方々が、そこまで追い込まれるに至った経緯を明らかにするとともに、そうした経緯を踏まえた上で適切な支援を構築・提供していくことを通じて、再度の自殺企図を防いでいくことが必要です。
これらを踏まえ、領域2では以下のような課題を想定・期待しています。
〈領域2課題例〉
・自殺ハイリスク層の解明ならびに適切な支援へとつなぐためのプログラムの構築・実践
・救急医療機関から地域の支援へと適切につなぐための支援プログラムの構築・実践
・医療従事者や自治体職員等支援者の支援スキル向上に向けたプログラムの開発と実践
・自傷・自殺未遂の手段別に見た対象者の特徴とそれを踏まえた支援プログラムの構築・実践
・自傷・自殺未遂等を繰り返す対象者を適切な支援につなぐための方策の構築と実践
・自殺リスクを早期に発見し適切な支援につなぐための方策の構築・実践
・妊産婦の自殺実態の解明とそれを踏まえた支援プログラムの構築・実践 など
- 領域3:デジタル関連技術(AI, IoT)やビッグデータを活用した自殺対策プログラムの構築・実践
昨今、AI をはじめとしたさまざまなデジタル関連技術が目覚ましい発展を遂げており、この活用の推進に向けた議論が国において進められています。自殺対策においても、これら技術の利用に係るリスクの管理を適切に行いつつ、医療関連のビッグデータはもとより、行政や民間が保有する業務データ、衛星画像等から得られるデータ、人流など人々の社会活動にかかわるデータなどを複合・駆使するなど、積極的に活用していくための方策を模索していくことで、対策の更なる推進につなげていくことが期待されます。
こうした社会状況を踏まえ、領域3では以下のような課題を想定・期待しています。
(参考) 行政の進化と革新のための生成AI の調達・利活用に係るガイドライン(令和7年5月27 日デジタル庁公開)
〈領域3課題例〉
・AI 技術を用いた自殺に係る相談記録の分析とそれに基づく相談対応の改善
・AI 技術を用いた自殺報道の分析と自殺防止プログラムの構築・実践
・メタバース等を活用した自殺防止相談事業の効果測定と改善プログラムの構築・実践
・AI 技術を活用した相談支援プログラムの構築・実践 など
- 特別枠:若手研究枠(自殺対策に関する自由テーマ)
若手研究者による自由な発想での自殺対策に資する研究を募集します。必ずしも上述した研究領域に囚われることなく、自由に研究課題を設定してください。なお、採択にあたっては、もっとも近いと思われる領域の研究課題として扱います。
4.応募書類・提出方法等
<公募要領>
<応募書類>
応募書類はこちらからダウンロードしてください。
ZIPファイルがダウンロードされます。ファイル解凍後、以下の3つの応募書類が格納されていることをご確認ください。
- 01_令和7年度委託研究公募申請書(研究計画書)_研究代表者氏名_所属機関名.docx
- 02_経費等内訳・項目申請書(研究代表者)_研究代表者氏名_所属機関名.xlsx
- 03_経費等内訳・項目申請書(研究分担者)_研究分担者氏名_研究代表者氏名.xlsx
<提出方法>
公募要領をよくご確認の上、応募書類を作成し、下記の「提出ファイル形式」に沿った形式で、E-mail に添付してご提出ください。
※ファイル名に、「研究代表者氏名」「所属機関名」を記載してください。
(例:01_令和7年度委託研究公募申請書(研究計画書)_生命太郎_○○大学.docx)
※提出書類に不備・不足があった場合でも、原則として事務局からご連絡は差し上げませんので、必ず研究代表者において提出書類をご確認ください。
| 応募書類 | 提出要件 | 提出ファイル形式 |
| 01_令和7年度委託研究公募申請書(研究計画書) | 提出必須 | WordとPDFの両方 |
| 02_経費等内訳・項目申請書(研究代表者) | 提出必須 | Excel |
| 03_経費等内訳・項目申請書(研究分担者) | 研究分担者に対して研究費の配分を行う場合のみ、配分を予定している研究分担者の人数分提出。 | Excel |
5.応募書類提出先
いのち支える自殺対策推進センター 革新的自殺研究推進プログラム公募受付窓口
E-mail:kobo_irpsc#jscp.or.jp (応募書類提出専用)
※迷惑メール対策のための表記ですので、メールを送信される際には、「#」を「@」に変換して送信してください。
※メールの件名に、「革新的自殺研究推進プログラム 委託研究公募申請書提出」と記載してください。
※提出する際のファイル名に、「研究代表者氏名」「所属機関名」を記載してください。
※上記アドレスにメールを送信すると自動応答メールが送信されます。自動応答メールを受信しない場合には、革新的自殺研究推進プログラム事務局(irpsc#jscp.or.jp)までご連絡をお願いいたします。 なお、メールアドレスの「#」を「@」に変換して送信してください。
6.よくある質問・問い合わせ先
多く寄せられるご質問への回答を掲載しました。令和7年度革新的自殺研究推進プログラム委託研究公募に関して不明点がございましたら、まずこちらをご確認ください。
質問文をクリックすると、回答が表示されます。
■ 革新的自殺研究推進プログラムという事業について
Q1:革新的自殺研究推進プログラムは競争的資金ですか。
A1:競争的資金を、「大学、国立研究開発法人等において、省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るもの」とすれば、革プロは競争的資金です。ただ、競争的資金を、「令和6年度・7年度競争的研究費制度一覧(省庁別予算)」のリストのみととらえれば、革プロは競争的資金ではありません。
■ 申請書類の作成(研究年度、研究開始日、作図等)について
Q2:本公募における「研究開始年度」とは、いつの年度を指すのでしょうか。
A2:令和7年度を指します。
Q3:本公募における「本年度」とは、いつの年度を指すのでしょうか。
A3:令和7年度を指します。
Q4:本年度の経費というのは令和7年度の経費を指すと理解してよろしいでしょうか。
A4:令和7年度の経費を指します。(研究の開始時期は、令和7年10月ごろを予定しています。)
Q5:公募申請書1ページ目「研究事業予定期間の開始日」はいつの日付を記載すればよいですか。
A5:採択決定日が未定のため、開始日は空欄のままご提出下さい。
(研究の開始時期は、令和7年10月ごろを予定しています。)
Q6:公募申請書(研究計画書)に図や表を掲載しても問題ありませんか。図や表は、字数制限に含まれないと考えてよろしいでしょうか。
A6:図や表を掲載いただくことは問題ありません。ただし図表は1つあたり400字として換算し、字数制限に含めてカウントしてください。
Q7:字数や行数の指定のない部分は、制限は特になく記載しても良いでしょうか。また「表」形式の部分で、行数が不足する場合追加してもよいでしょうか。
A7:字数や行数等の制限が特に設けられていない箇所については、必要な範囲で記載いただいて差し支えありません。表形式の記載欄についても、必要に応じて行の追加を行っていただいて構いません。ページ数が増えることについても問題ありません。
Q8:各用紙にある記入内容についての説明記載はそのまま残したほうがよいでしょうか。
A8:記入内容についての説明記載は削除の上、申請書の作成をお願いいたします。
■ 応募資格・体制について
Q9:若手研究枠は、研究分担者も若手の必要がありますか。
A9:研究分担者が若手である必要は必ずしもありません。研究代表者が若手であれば、分担研究者の方が若手であるかどうかにかかわらず、ご応募いただけます。
Q10:研究課題の申請を行う際、所属機関の了承を得る必要があるとの記載がありますが、この時了承を得る「研究代表機関の長」は、大学であれば学部長でよいでしょうか。
A10:了承を得る「研究代表機関の長」は、原則として、学長、理事長等を想定しています。あるいは、各機関の規定等で学長等以外に契約締結の権限を有する方がいれば、その方の了承でも構いません。
なお、申請時点で所属機関の了承を証明する書類の提出等は必要ありません。ただし、採択された場合には、所属機関が正式に委託を受けられることが前提となりますので、あらかじめ所属機関内での必要な手続きを確認のうえ、事前にご対応いただきますようお願いいたします。
Q11:「経理事務担当者」と「秘書等連絡先」を同一者で兼ねてもよいでしょうか。
A11:研究代表者と所属機関が同じ方であれば、同一方が兼任しても差し支えありません。
Q12:研究代表者の所属機関内に研究倫理審査委員会を有していない場合でも、本公募に申請できますか。また、その場合、外部機関に倫理審査を委託しても問題ないですか。
A12:所属機関内に研究倫理審査委員会を有していない場合でも、研究分担者の所属機関内等の外部機関にて研究倫理審査を受けることが可能である場合には、ご応募いただくことができます。
なお、申請時点で研究倫理審査を終えている必要はありません。
Q13:大学院生などの学生でも、応募資格はありますか。
A13:大学院生などの学生は、原則として研究代表者および研究分担者としての申請はできません。ただし、研究協力者としての参加は可能です。
(1)研究代表者としての申請: 原則としてできません。ただし、以下の条件を満たす場合は申請いただけます。
・所属する研究機関において研究活動を行うことを本務とする職に就いており(例:大学教員、企業等の研究者)、学生の身分も有する者
(2)研究分担者としての申請:原則としてできません。ただし、以下のいずれかに該当する場合は申請いただけます。
・所属する研究機関において研究活動を本務とする職に就いており、かつ学生の身分も有する者(例:大学教員、企業等の研究者)
・日本学術振興会特別研究員、または任期付きポスト(ポスドク等)で研究機関に雇用され、職責を有する大学院生
(3)研究協力者:参加いただけます。
■ 研究費について
Q14:直接経費の申請上限額は400万となっていますが、400万円は3年間の合計でしょうか、それとも各年度ごとの上限でしょうか。
A14:各年度ごとに400万円を上限として申請いただくことが可能です。
Q15:採択された場合、申請額通りの金額の研究費が委託されますか。
A15:採択後に実際に委託される金額が、申請額よりも少なくなる場合があります。その点はあらかじめご了承ください。
Q16:他の研究費に応募している場合でも、応募は可能でしょうか。
A16:他の研究費に応募・受入中でも、応募していただくことは可能です。ただし、必ず公募申請書「9.研究費の応募・受入等の状況」に状況を記載してください。その際に、「既に応募中・受入中(予定含む)の研究課題の内容と、本応募研究課題との内容の相違点」を明確にした上で、他の研究費に加えて本応募研究課題に応募する理由を明確に記載してください。
Q17:「7. 研究費の実績」および「8. 研究費の応募・受入等の状況」に記載する「研究経費」は、「直接経費」のみを指しますか?それとも、「直接経費に間接経費を加えた総額」を記載すべきでしょうか。また、記載対象となる研究代表者(申請者)の研究は、具体的にどのようなものを含めればよいでしょうか。
A17:「7. 研究費の実績」および「8. 研究費の応募・受入等の状況」に記載いただく「研究経費」は、研究代表者(申請者)本人に配分された「直接経費」のみを対象としてください。 なお、本申請に関わる他の研究分担者等が獲得した研究については、記載の必要はありません。
■ 契約及び中間評価について
Q18:3年間の研究が採択されたら、契約は1回で3年間分まとめて行われますか。
A18:3年間の研究が採択された場合でも、契約は毎年度ごとに締結する必要があります。
Q19:採択された3年間の研究助成が、途中で打ち切りになる場合もありますか。
A19:複数年度に及ぶ研究課題については、「当初の研究計画通りに進行しているかどうか、その年度内に達成すべき事項が達成できているかどうか」等を客観的かつ公正に判断するために年度ごとに中間評価が行われます。中間評価の結果によっては、次年度の研究が中止となる場合もあります。
上記「よくあるご質問」に記載がない内容でご質問がある場合、下記メールアドレスまでご連絡のほど、よろしくお願いいたします。
革新的自殺研究推進プログラム事務局
E-mail:irpsc#jscp.or.jp
※迷惑メール対策のための表記ですので、メールを送信される際には「#」を「@」に変換して送信してください。