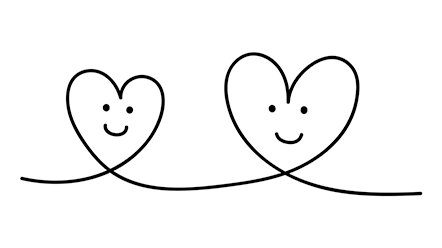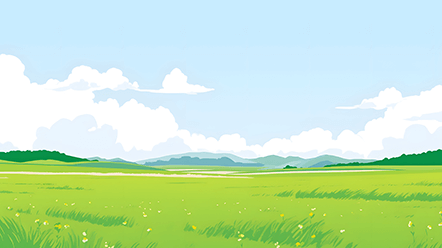職員紹介


【職員インタビュー】センター長補佐:村松裕文
「生きることの包括的支援」を体現し、「点」をつなぐ存在でありたい

〈プロフィール〉村松裕文(むらまつ・ひろふみ)
神奈川県出身。学習院大学文学部卒業後、2007年4月厚生労働省の職員となる。精神保健における予算執行業務に始まり、東日本大震災直後の食品安全行政、予防接種後の健康被害救済給付、熊本地震を踏まえた災害に強い地域保健の枠組みづくりといった業務に従事。2018〜2021年度にかけては消費者庁に出向し、食品表示法改正に関わるほか、食物アレルギー表示制度の見直し(くるみの義務表示化)などにも関わった。 2022年4月より厚生労働省自殺対策推進室にて業務に従事。2024年4月にJSCPに入職し、2025年4月より現職。
── センター長補佐としての仕事について、教えてください
村松)一言で表現するならば、「生きることの包括的支援」につながる取り組みであれば、JSCP内の各部署の垣根を越えて「なんでもやる」人だと思います。
自殺対策基本法第2条に規定されている基本理念でも謳われているとおり、自殺対策は「生きることの包括的支援」であり、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならないものです。喫緊の課題となっている児童生徒の自殺者数の増加について、自殺統計のうち原因・動機別の分析を紐解いてみると、「学校問題」、「家庭問題」、また、そうした問題に起因する心身の不調も含む「健康問題」などの数字が計上されています。このことからも、自殺対策を進めるためには、単一の行政施策によるアプローチだけでは効果は限定的であり、様々な施策領域が複層的に連携・協働を図ることが重要だと考えられます。
ただ、国や地方自治体の組織において、部署を超えて連携・協働を果たし、整合性を持った取り組みを講じていくことは並大抵のことではありません。「とある部署の、とある職員」一人が声を上げても、残念ながらそれだけでは連携・協働を進めることは非常に困難です。JSCPは、そうした取り組みを後押しする数々の支援を行っています。
JSCPは、2025年度現在で、自殺総合対策部、調査研究推進部、地域連携推進部、総務部の4部から構成されており、それぞれに様々な背景・専門性を持った職員が在籍しています。前述のとおり自殺対策基本法の基本理念では、自殺対策は、生きることの包括的な支援として、「保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない」と規定されていますが、まさにJSCPは、「生きることの包括的支援」の縮図とも言える多様性に満ちた職場であると考えています。
その中にあって、私は医師でもなければ、法律家でもない。各方面への調整業務に勤しんできただけの人間です。しかし、知識の上では専門職にも負けじと専門書を読み漁りながら、医系技官や看護系技官とも連携しながら、数々の苦難を乗り越えてきた経験は、この職場においても活きている部分があるのではないかと実感しています。
── 具体的な役割は?

村松)私のミッションは、大きく3つあります。
1つは、地域連携推進部の統括的立場です。地域連携推進部は、住民のいのちと暮らしを守る現場である地方自治体に対して、自殺総合対策大綱や「こどもの自殺対策緊急強化プラン」などを踏まえつつ、自殺対策の取り組みが効果的かつ効率的に進むよう支援を行っています。
2つ目は、自殺未遂者に関わる多職種の方々に、「自殺未遂者ケア」を習得していただくための研修の管理。
3つ目は、こどもの自殺対策を強力に進める観点で、2025年6月11日に公布された改正自殺対策基本法の施行後に向けた準備を、関係各省庁と連携しながら進めていくことです。これは、JSCP内の組織横断的かつ、今年度(2025年度)最大のミッションです。
このように、課せられている業務は広範にわたりますが、法の基本理念である「生きることの包括的支援」を体現し、それぞれ「点」であったものを内外問わずつなぎとめて「線」や「面」にしていく存在でありたいと思っています。
── JSCPで働く前は、どんなことをしていましたか?
村松)祖父を指定難病である筋委縮性側索硬化症(ALS)で亡くしました。当時は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」の影も形もない頃で、患者への向き合い方についての情報も十分になく、無力感に苛まれたのを覚えています。そうしたこともあって、当初大学院に進学して歴史学を極めようと思っていましたが、国の職員として、特に公衆衛生に関わる制度の枠組みに何らかの形で関わりたいという思いで、厚生労働省に入省しました。
在職中に難病対策に直接関わることはありませんでしたが、それでも、予防接種による健康被害のあった被害者や食物アレルギー患者会の方々との面談など、本当にいろいろなお声をいただきながら、業務に取り組んできました。
そうした内外問わずの調整業務や、予算に関連する業務などについて、公務員というハードウェアとしての基盤を固めつつも、概ね2年おきの人事異動により全く異なるソフトウェア(異なる領域という意味)を組み込んで、文字通り「なんでも屋」として働いてきました。あとになって思えば、公務員としてのこれまでの働き方は、「生きることの包括的支援」に通ずるものであったのかなと感じます。
── 自殺対策に関わるようになった時期や、きっかけは?
村松)消費者庁に出向中の2020年に、父をがんで亡くしました。仕事人間ながらも、温かく、今でも「あの人を超えられることは一生かけてもないだろうな」と思えるくらいに尊敬している父でした。病室に2か月ほど寝泊まりし、リモートワークを活用しながら、父が生命を全うするその日に至るまで丁寧に過ごすことができました。
2022年4月に厚生労働省に帰任し、自殺対策推進室の係長になりましたが、父の死に向き合ってから、自分自身、これからの生き方について考えることも多くなっていたように思います。「たまたま」異動してきた部署だったのかもしれません。しかし、直前に身近な死に接したことや、20年弱ですが仕事でいろいろな局面に接してきたこともあってか、「生きることの包括的支援」の意味を知ったとき、公務員が行うべきことはまさに、すべてここに通じているのではないかと感じました。そして、その深さに次第に惹かれ、自殺対策の世界に身を投じる決意をしました。
── 自殺対策への思いを聞かせてください
村松)自殺対策が社会実装されて20年近くが経過し、各主体が取り組みを進めていくことで、私が公務員として社会人をスタートしたころには年間3万人を超えていた自殺者数は、2万人を下回るかというところまで来ています。これは各主体が連携・協働を図りながら、総力を結集してきた成果の表れであると考えています。
しかし、亡くなられた方々は生き返ることはありません。自殺で亡くなる人の数が累積する速度が多少減速しているに過ぎず、児童生徒の自殺者数が過去最多となっていることなどを常に意識し、改正された自殺対策基本法を武器に関係各省庁と連携しながら、対策を講じていきたいと考えています。
地域における自殺対策力の向上を支援する様々な知見がJSCPにはあります。ぜひ、地方自治体等の皆様に信頼を置いていただき、JSCPを使い倒していただけるよう、私自身、限界を定めず、一緒に悩み、それら課題を突破していくお手伝いができればと考えています。
■職員インタビューのバックナンバーは、こちら