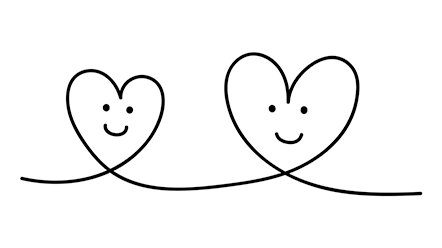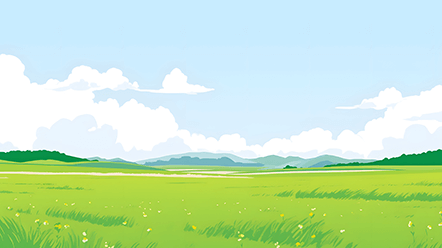研修・会議


【開催レポート】令和7年度開催 自殺対策推進レアール(令和6年度委託研究成果報告会)
JSCPは、2025年8月29日、9月2日・4日の3日間にわたり、革新的自殺研究推進プログラム「自殺対策推進レアール(※1)(令和6年度委託研究成果報告会)」をオンラインで開催しました。
「革新的自殺研究推進プログラム」は、科学的根拠(エビデンス)に基づいた政策立案及び社会還元に資する研究を推進するため、自殺対策関連分野の研究者等への公募による委託研究を行うものです。今回は、2024(令和6)年度に取り組んだ3つの領域における、計11の研究課題の成果報告会を実施。自殺対策の現場を担う地方自治体の自殺対策担当者や自殺対策関連学会に所属する方々を中心に、延べ約800人(領域1:約350人、領域2:約250人、領域3:約200人)にご参加いただきました。
各領域の開催日
- 領域1(子ども・若者に対する自殺対策) :2025年8月29日
- 領域2(自殺ハイリスク群の実態分析とアプローチ) :2025年9月2日
- 領域3(ビッグデータ・AI等を活用した自殺対策) :2025年9月4日



各報告会の冒頭で、JSCP代表理事の清水康之は、「革新的自殺研究推進プログラムにおける研究を通じて、自殺対策の『現場』と『研究』と『政策』の連動性を向上させることで、対策の更なる推進を目指しており、レアールという場がそのための有効な情報共有や意見交換の場となることを期待している」と挨拶しました。その上で、参加者から寄せられる意見や質問、それを踏まえた研究代表者とのやりとりが、研究と自殺対策の現場における取り組みとの連動性を高め、現場での活用や社会実装へとつなげていくための重要な一歩となるとし、積極的な参加を呼びかけました。
続いて、厚生労働省大臣官房参事官(自殺対策担当)の宮崎千晶氏が挨拶。自殺をめぐる現状(自殺者数の推移と、それを踏まえて国で進めている各種施策の状況等)の紹介と、レアールにおける研究報告及びそれに対する参加者からの質問と意見交換の意義、さらに委託研究の成果が自殺対策に資するような形で還元されることへの期待を述べました。

それぞれの報告会では、2024年度までの各領域のプログラムディレクター(領域1:佐々木剛氏(千葉大学附属病院)、領域2:藤森麻衣子氏(国立がん研究センター)、領域3:久保順也氏(宮城教育大学))が座長を務め、課題別の研究成果について報告。3領域全体で計11に及ぶ課題の研究代表者が、それぞれの研究を通じてこれまでに得られた成果や知見等について説明しました。質疑応答では、参加者から多くの質問や意見が寄せられ、活発な議論が行われました。
研究成果報告の後は各研究代表者を中心に、JSCP代表理事の清水と調査研究推進部長の小牧奈津子も加わる形で、領域ごとの全体討議を実施。領域1では、近年、事態が非常に深刻なこどもや若者の自殺を防ぐ上で、様々な関係者同士が連携をすることの重要性と、それを実現する上での課題、さらにはそれを克服するための工夫等について意見を交わしました。領域2では、自殺のハイリスク群の実態分析を通じて見えてきた知見を踏まえ、今後はリスクを抱えた特定の集団に対するアプローチと併せて、その周囲に存在する身近な人々や支援者等も含めた支援の必要性やそのあり方等について検討。領域3では、様々なデータを組み合わせて分析等を行うことを通じて、これまでに見えてこなかった課題を可視化するとともに、それを踏まえていかなる取り組みを講じていくかについて議論が行われました。
いずれの全体討議も、研究を通じて得られた成果や知見を、どのように現場へと届け、いかに活用して、現場の抱える課題の解決や取り組みの推進につなげていくかという、「現場」と「研究」と「政策」の連動性の向上に向けて、参加者も含めてともに考えるという貴重な場となりました。



JSCPでは、今後も革新的自殺研究推進プログラムを通じて、自殺対策の実践的な研究(政策研究)をもとに自殺総合対策の推進に資するデータ及び科学的根拠を収集することにより、自殺総合対策の推進を図っていきます。
※1 「自殺対策推進レアール」は、革新的自殺研究推進プログラムの委託研究成果報告会の名称です。「レアール」という言葉はフランス語で中央市場(Les Halles)を意味しますが、本プログラムでは研究報告会という場が、自殺対策の「現場」と「研究」と「政策」との連動性を向上させるための、非常に有効な情報共有や意見交換の場となることを期待して、この名をつけています。
《委託研究一覧》
【領域1】子ども・若者に対する自殺対策(※所属・役職は開催当時)
| 課題番号 | 研究課題名 | 研究代表者 | 所属・役職 |
| R4-1-2 | SOSの出し方教育における地域連携モデルの開発 | 江畑慎吾 | 中京学院大学 短期大学部 保育科 准教授 |
| R4-1-3 | 児童生徒の自殺リスク予測アルゴリズムの解明:自殺リスク評価ツール(RAMPS)を活用した全国小中高等学校での大規模実証研究によって | 北川裕子 | 東京大学大学院 教育学研究科 身体教育学コース 健康教育学分野 特任助教 |
| R4-1-4 | 全小児科医を対象とした大規模調査:「小児科による自殺防止セーフティネット」構築へ向けた課題整理と政策提言に関する研究 | 呉 宗憲 | 東京医科大学 小児科・思春期科学分野 准教授 |
| R4-1-5 | 子どもの抑うつに対する遠隔メンタルヘルスケアの社会実装と早期受療システム整備-KOKOROBOと子どもの精神疾患レジストリ連携- | 佐々木剛 | 千葉大学医学部附属病院 こどものこころ診療部 准教授 |
| R4-1-7 | 学校において教職員がゲートキーパーとして機能するためには何が必要か?―チーム学校によるマルチレベルな自殺予防体制の支援・組織モデルの構築― | 目久田純一 | 梅花女子大学 心理こども学部 こども教育学科 准教授 |
【領域2】自殺ハイリスク群の実態分析とアプローチ(※所属・役職は開催当時)
| 課題番号 | 研究課題名 | 研究代表者 | 所属・役職 |
| R4-2-2 | 非行を有するハイリスクな青少年の自殺・自傷行為の理解・予防・対応策に関する包括的な検討 | 高橋 哲 | お茶の水女子大学 基幹研究院人間科学系 教授 |
| R4-2-3 | がん患者の自殺に関する全国実態分析とがん診療病院自殺対策プログラムの検討 | 藤森麻衣子 | 国立研究開発法人国立がん研究センター がん対策研究所サバイバーシップ研究部 支持・緩和・心のケア研究室 室長 |
【領域3】ビッグデータ・AI 等を活用した自殺対策(※所属・役職は開催当時)
| 課題番号 | 研究課題名 | 研究代表者 | 所属・役職 |
| R4-3-1 | 視覚情報のAI分析を活用したメンタルヘルスDXプロジェクト | 奧山純子 | 尚絅学院大学 総合人間科学系 教授 |
| R4-3-2 | IoT活用による子どもの援助希求行動の促進に関する研究 | 久保順也 | 宮城教育大学大学院 高度教職実践専攻(教職大学院) 教授 |
| R4-3-4 | 過量服薬のゲートキーパーの養成を目指したビッグデータ解析と新規養成システムの構築:地域の薬局を「気付き」と「傾聴」の拠点とした過量服薬の防止 | 永島一輝 | 千葉大学大学院 薬学研究院 先端実践薬学講座 実務薬学研究室 助教 |
| R4-3-5 | 兵庫県における医療ビッグデータと法医学データを組み合わせたコホートデータベースを用いたリアルワールドデータによる自殺リスクの検討 | 宮森大輔 | 広島大学病院 総合内科・総合診療科 診療講師 |