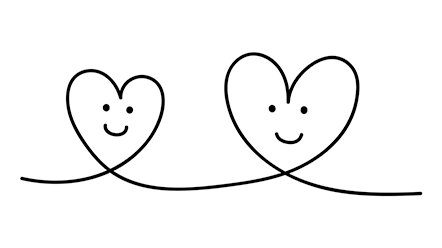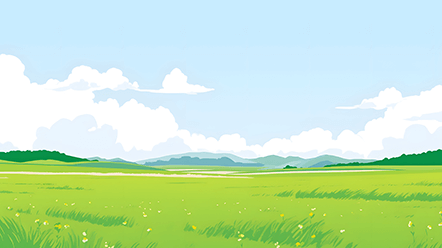研修・会議


【開催レポート】令和7年度「自殺対策と他制度等との連携構築に関する研修会」 ~地域福祉・消費者行政を含めた「生きることの包括的な支援」へ~

JSCPは、2025年9月26日、令和7年度「自殺対策と他制度等との連携構築に関する研修会」をオンラインで開催しました。この研修会は、自殺対策と消費者行政、地域福祉・生活困窮者自立支援制度(重層的支援体制整備事業含む)等における関連施策との連携強化を図るため、関係機関がともに学び、自治体の包括的支援に関する施策の展開の一助とすることを目的としたもので、今回が初めての開催になります。当日は全国の市区町村や保健所等の自殺対策担当者や、消費者行政、生活困窮者自立支援制度等に携わる職員・関係機関を中心に、約700人が参加しました。
各省庁が施策について説明
研修の前半では、各省庁が施策について説明。厚生労働省大臣官房参事官(自殺対策担当)の宮崎千晶氏は、自殺者数の動向及び自殺の原因・背景を踏まえ、各分野の専門性を発揮して連携することの重要性について、消費者庁地方協力課長の赤井久宣氏は、相談事例をまじえながら消費生活相談の状況や消費者安全確保地域協議会の取り組み、福祉と消費がつながる必要性について、厚生労働省社会・援護局地域福祉課長の野﨑伸一氏は、地域共生社会の実現に向けた取り組みの背景と施策、誰も取り残さない包括的な支援体制の構築へのチャレンジについて、それぞれ紹介しました。
自治体現場からの報告とディスカッション
後半は、自治体現場からの報告とディスカッションを実施。まず東京都足立区福祉まるごと相談課長の大北有慶氏が、「足立区版『まるごと相談』の現在地」をテーマに、重層事業を活用した「福祉まるごと相談課」の体制や相談実績、個別事例の紹介とこれからの展開について報告。その後、説明・報告の登壇者にJSCP代表理事の清水康之が加わり(進行:JSCP地域連携推進部の生水裕美)、事前アンケートに寄せられた課題や質問を踏まえてディスカッションを行い、それぞれの視点から活発な意見交換をしました。
最後に参加者に向けたメッセージとして、宮崎氏からは「現場は連携が必要と分かるからこそもどかしさを感じているのだと思う。連携をこれから政策の中心と位置づけてしっかりやっていきたい」、赤井氏からは「福祉の皆さんには、消費者問題の視点を日常の業務の中に入れてもらいたいし、厚労省とも連携を深めたい」、野崎氏からは「制度(政策論)と実践(運動論)は両輪である。今は十分にできていないことがあっても小さな働きかけが将来を変えていく。自治体現場の連携に活用できるよう国レベルでも各省庁の考え方を共有しメッセージを出していきたい」、大北氏からは「今まで消費生活センターとの関わりはなかったが、声をかけて支援会議等に参加してもらうなど連携を形にしていきたい」、最後に清水からは「今回を第1回としてぜひ第2回をしたい。国が心臓とすれば地域住民は細胞、基礎自治体は毛細血管、都道府県は大動脈。困難な状況にある人が支援にたどり着けるように、これからもさらに取り組みを進めていきたい」との言葉がありました。
JSCPでは、今後も地域の様々な関係者が連携し、「生きることの包括的支援」として自殺対策を推進できるよう、各種研修の開催等を通じて支援していきます。