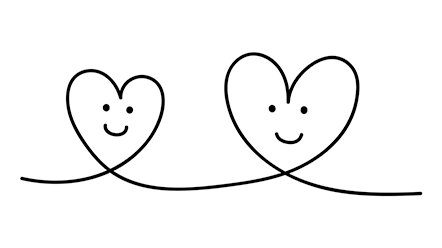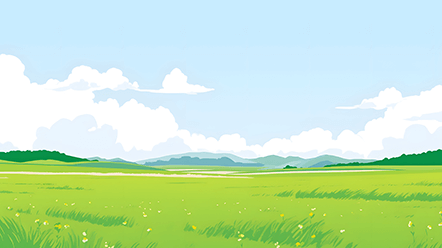SPECIAL


【記事公開】SNSがいのちを救う︖――インフルエンサー投稿がもたらす「パパゲーノ効果」の可能性
「Yahoo!ニュース エキスパート」で2025年9月8日に公開した記事を転載しています。
(写真はイメージ)
SNSが若者のこころに与える影響について、しばしばその危険性が注目されています。実際、SNSの過度な利用はこどもや若者のメンタルヘルスの悪化につながることを多くの研究が指摘しており、国によっては、法律で若年層の使用を制限する動きも広がっています。
しかし、SNS投稿は使い方によって、プラスに働くこともあります。希望をもたらすSNS投稿がいのちを救う可能性があるという研究結果が、公表されました。
オーストリア・ウィーン大学のFlorian Arendtらの研究で、ソーシャルメディア・インフルエンサーによる「希望・回復・再起」(hope, healing, and recovery)の物語が、自殺念慮(「死にたい」気持ち)を減少させ、援助を求める意図を高める可能性が示されました。この研究の詳細は、2025年2月に学術誌『Social Science & Medicine』でオンライン公開されました(論文に関する情報は記事末尾に記載します)。
メディアがもたらす二つの効果
メディアが自殺に与える影響には、「ウェルテル効果」と「パパゲーノ効果」という二つの側面が報告されています。ウェルテル効果は、有名人の自殺報道などセンセーショナルな報道が模倣行動を誘発し、自殺者数が増加する現象です。一方パパゲーノ効果は、自殺危機からの回復を描いた物語が、読者や視聴者の自殺念慮(「死にたい」気持ち)を減少させ、自殺を抑止する現象です。論文では、メディアは「諸刃の剣である」としています。
論文によると、過去の自殺報道に関する研究は、大部分がウェルテル効果に焦点を当ててきました。パパゲーノ効果は、2010年に提唱された比較的新しいもので、ウェルテル効果に比べると研究はまだ少ないものの、これまで新聞、テレビなどの伝統的メディア、映画、音楽などで確認されてきました。
今回の研究でArendtらは、ソーシャルメディアに焦点を当てました。研究チームは、SNSでの投稿はこれまで伝統的メディアが提供してきた「希望・回復・再起」の物語に比べ非常に短いものの、SNSインフルエンサーらの体験談はフォロワーにとって信頼性が高い情報源であり、パパゲーノ効果を生じさせる可能性があるのではないかと考えました。
実験の概要と結果
Arendtらの実験では、18歳~65歳の354人を対象に、過去に自殺未遂の経験がある架空のインフルエンサー「ケビン・ハインリヒ」による希望、回復、再起に関する10のソーシャルメディア投稿を閲覧する介入群と、無関係な投稿(ボーイスカウトに関する内容)を閲覧する対照群を比較しました。
その結果、介入群では自殺念慮が有意に減少しました。特に、もともと自殺念慮が高かった人ほどより強い減少が見られ、援助を求める意図も増加しました。この効果は、精神保健の専門家や電話相談窓口、家族、友人など、あらゆる支援者(機関)に対して観察されました。
男女ともに同様の結果が得られ、女性においては男性よりも強い効果が認められました。これにより、インフルエンサーが男性であっても女性への効果を下げるものではないことが示唆されました。
ただし論文では、この研究で測定されたのは「自殺念慮」の変化であり、実際の自殺行動に直接つながるかどうかについては、今後の検証が必要である点も記されています。また、自殺未遂の実体験を持たないインフルエンサーの投稿にも同様の効果があるのかや、効果の持続性などについても今後の検討が必要だとしています。
インフルエンサーの皆さんへ──あなたの投稿が誰かのいのちを救うかもしれません
この研究は、自殺の危機から回復した経験を持つインフルエンサーが、フォロワーらにとって「予防的なロールモデル」となり、「自分も乗り越えられるかもしれない」という希望を与える可能性を示しています。
今回の実験で用いられた架空のインフルエンサー「ケビン・ハインリヒ」は、実在のアメリカのインフルエンサー、ケビン・ハインズ氏がモデルとなっています。ハインズ氏は、自殺未遂の経験を語る講演活動や映画制作などを行っており、インスタグラム(@kevinhinesstory)で8万人以上のフォロワーがいます。論文では、代表的な投稿として以下の5つを紹介しています。
「人生を終わらせることは決して解決策ではありません。」 (“Ending your life is never a solution.”)、「私の使命は、死を乗り越えた自分の物語を共有することです。」(“My purpose: Sharing my story of surviving death.”)、「痛みは必ず乗り越えられます。私たちは人々に目を向けるべきです。」( “You can always survive the pain. We must look to the people.”)、「あなたは誰かの命を救うことができます。」(“You can save someone’s life.”)、「明日もここにいてください。」(“Always be there tomorrow.”)。
インフルエンサーの皆さんの投稿が、誰かのつらい気持ちにそっと寄り添い、「生きる」方向に、背中を押すかもしれません。SNS上には、不安を増幅させる情報が少なくありません。だからこそ、経験に基づく希望のメッセージを届けることは、大きな意味を持つのではないでしょうか。あなたの投稿が、誰かのいのちを救うかもしれません。
デジタル時代の自殺予防戦略
Arendtらは、ソーシャルメディアが自殺予防の新たなプラットフォームとなり得ることを示唆しています。そして、「ソーシャルメディアが特に若年層において重要な役割を果たしている事実を踏まえると、ソーシャルメディア・インフルエンサーを通じた自殺予防の取り組みは、デジタル時代における自殺予防の有望な戦略となり得る」「このアプローチは、世界中の多くのユーザーに、24時間365日、事実上費用なしで届けることが可能だ」と結論付けています。
専門家の意見
自殺報道の研究に詳しい和光大学の末木新教授(心理学、自殺学)は、Arendtらの研究結果について、次のように話しています。
「パパゲーノ効果に関する研究の蓄積はまだ浅く(少なくともウェルテル効果に比べて)、まだ発展途上の概念です。どのような状況に置かれている人に対して、どんな物語が届くことが、生きる希望をもたらすことにつながるのかが、必ずしも明確になっていません。しかし、癒しや回復の物語を伝えることは、誰かが自殺で亡くなった物語が伝えられることに比べて、副作用が小さいことは明らかです。もっと言えば、あなたが癒され回復した物語は、誰かの生きる希望になる可能性だってあるのです。SNSでの影響力のあるインフルエンサーであれば、なおのことでしょう。」
【文・山寺香】
|
■本記事は、以下の学術論文に基づいて構成されています。 論文名: Social media influencers and the Papageno effect: Experimental evidence for the suicide-preventive impact of social media posts on hope, healing, and recovery 著者: Florian Arendt, Benedikt Till, Armin Gutsch, Thomas Niederkrotenthaler 掲載誌: 『Social Science & Medicine』 発表年月: 2025年2月(オンライン公開日) |
ーーーーーーーーーーー
◆記事を読んでつらい気持ちになったら。気持ちを落ち着ける方法や相談窓口などを紹介しています。
「こころのオンライン避難所」https://jscp.or.jp/lp/selfcare/
◆生きるのがしんどいと感じているこども・若者向けの Web空間で、安心して存在できるオンライン上の居場所。絵本作家のヨシタケシンスケさんが全面協力。
「かくれてしまえばいいのです」https://kakurega.lifelink.or.jp/
◆つらい気持ちを相談できる場所があります。
<電話やSNSによる相談窓口>
・#いのちSOS(電話相談)https://www.lifelink.or.jp/inochisos/
・チャイルドライン(電話相談など)https://childline.or.jp/
・生きづらびっと(SNS相談)https://yorisoi-chat.jp/
・あなたのいばしょ(SNS相談)https://talkme.jp/
・こころのほっとチャット(SNS相談)https://www.npo-tms.or.jp/service/sns.html
・10代20代の女の子専用LINE(SNS相談)https://page.line.me/ahl0608p?openQrModal=true
<相談窓口をまとめたページ>
・厚生労働省 まもろうよこころ https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/