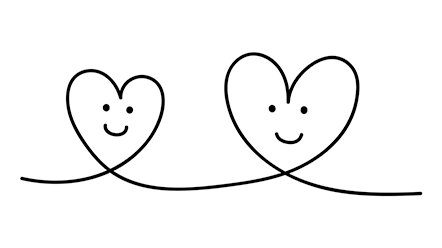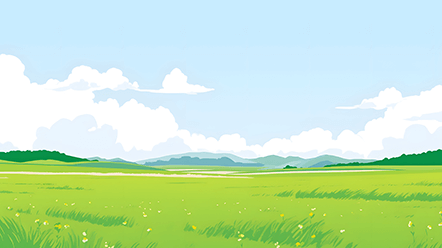自殺対策について


- HOME
- 自殺対策について
日本における自殺の実情と自殺対策の概要を「基礎知識」として知っていただくためのページです。自殺は、その多くが「追い込まれた末の死」であること。そのために、自殺対策とは「生きることの包括的な支援」であること。また、これまで「日本の自殺対策がどのように歩んできたか」や、いま直面している「喫緊の課題」等について解説しています。
本ページを通じて、日本の自殺問題・自殺対策の「過去・現在・未来」を知っていただければと思います。
-
自殺の実態
日本の自殺者数の推移
我が国の自殺者数は、1998年以降、14年連続して3万人を超える状態が続いていましたが、2012年に15年ぶりに3万人を下回りました。また、2010年以降は10年連続で減少し、2019年は2万169人と、1978年の統計開始以来最少となりました。ところが、新型コロナウイルス感染症の拡大が深刻化した2020年は2万1,081人となり、11年ぶりに増加に転じました。その後も2万人を超える水準で推移し、2024年は2万320人となっていましたが、2026年1月に公表された2025年の暫定値は1万9,097人となり、このまま確定すると統計開始以来初めて2万人を下回ることになります。
とはいえ、日本の自殺死亡率は国際的にみるとまだ高く、毎日新たに50人以上の方が自ら命を絶っている状況が続いています。また、近年深刻さを増しているこども・若者の自殺も喫緊の課題です。■ 厚生労働省が公表した2025年の年間自殺者数の暫定値はこちらからご覧いただけます。
-
いのち支える自殺対策とは
自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因(自殺のリスク要因)」を減らし、「生きることの促進要因(自殺に対する保護要因)」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、「地域連携のレベル」、「社会制度のレベル」、それぞれにおいて強力に、かつそれらを総合的に推進するものとされています(「自殺総合対策大綱」より)。そのためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取り組みが重要であり、そうした「生きることの包括的な支援」を実施するためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要があります。
-
自殺対策の歩み
「自殺する奴は弱い人間だ」「自ら勝手に死んだんだ」―――。自殺は、かつては「個人の問題」と認識されがちでしたが、2006年10月に自殺対策基本法(以下「基本法」という。)が施行されて以降、広く「社会の問題」と認識されるようになり、国を挙げて自殺対策が総合的に推進されるようになりました。2016年には基本法が改正され、すべての都道府県及び市町村が自殺対策計画を策定することとなりました(地域自殺対策計画策定の義務化)。このように我が国の自殺対策は、基本法第1条(目的)に謳われる「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」に向けて、日々進化し続けています。