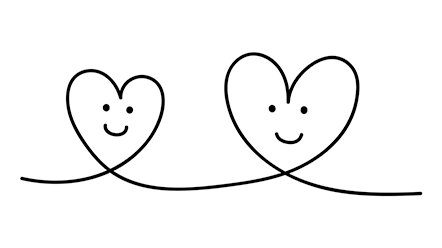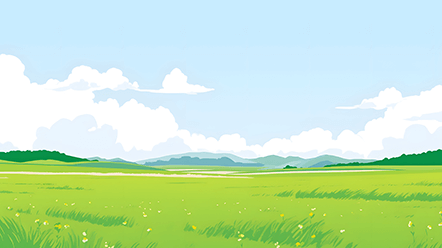啓発・提言等


WHO自殺報道ガイドライン
報道関係者向けガイドライン
自殺に関する報道や情報は、それがセンセーショナルに伝えられることによって、模倣自殺を誘発し自殺者数の増加につながってしまうことがあります。こうした現象は「ウェルテル効果」と呼ばれ、1974年以降に世界各地の多くの研究で実証されています。一方、自殺を考えるほど追い詰められた人が死なずに生きる道を選んだ体験談などを伝えることが自殺を抑止する現象は「パパゲーノ効果」と呼ばれ、2010年に提唱されて以降注目されています。
WHOは、こうしたメディア報道のマイナスの側面を最小化し、プラスの側面を最大化するため、自殺報道に関するメディアガイドライン「メディア関係者に向けた自殺対策推進のための手引き」(WHO自殺報道ガイドライン)を公開しています。このガイドラインでは、メディア関係者が自殺関連報道をする際の「やるべきこと」、「やってはいけないこと」などがまとめられています。
映像制作者や舞台・映像関係者向けガイドライン
また、WHOでは、映像制作者や舞台・映像関係者向けに、自殺対策に関するガイドライン「映画制作者と舞台・映像関係者に向けた自殺対策推進のための手引き」を作成しています。この手引きでは、テレビ番組、映画、ドキュメンタリー、演劇などで自殺や自傷に関する内容の企画・制作を行う者を対象として、実際に起きた自殺・フィクションの自殺を描写する際に「留意すべきこと」などがまとめられています。
■厚生労働省HP すぐわかる要点(クイック・レファレンス・ポイント)
各国のガイドライン
このほか、各国では、WHO自殺報道ガイドライン(初版:2000年)の発行後、それぞれの国の状況に合わせたガイドラインが作成されています。
■主なガイドラインの概要をまとめています
※JSCPが収集した情報を基に作成しました。すべてのガイドラインを網羅しているわけではありません(更新:2023年8月10日)