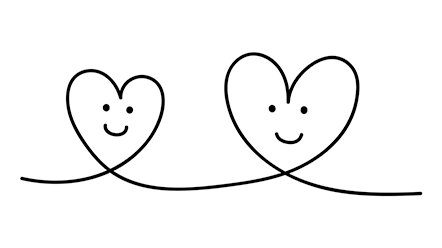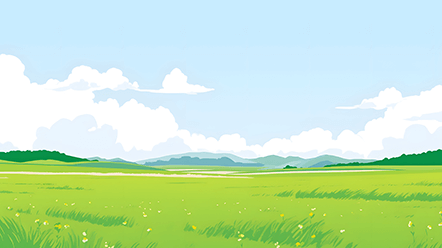職員紹介


【職員インタビュー】業務改善室長:北爪愛子SEから自殺対策へ 「声」を拾って組織を変える
 〈プロフィール〉
〈プロフィール〉
北爪 愛子(きたづめ・あいこ)
東京都出身。大学時代にNPO法人「自殺対策支援センター ライフリンク」のインターンとしていじめ対策プロジェクトなどに関わる。大学卒業後、保険業界のシステムエンジニアとして約7年間勤務し、プロジェクト管理などを行う。2020年4月よりJSCPに在籍、同年5月から総務部業務改善室長。
――業務改善室の役割や、主な業務について教えてください
北爪)一言で表現すると「JSCPの何でも屋」です。JSCPの職員は、民間企業、教育、医療、行政、メディアなど多様なバックグラウンドを持っており、各職員の経験を存分に生かせる環境を整えることが、自殺対策の推進につながると考えています。業務改善室では、職員が自殺対策を効率的・効果的に推進していくために必要な職員向け研修会の企画やメンタルヘルス対策、人事評価制度の構築、生成AIの活用推進などを進めてきました。また、他の総務部の職員と共に、人事・法務・経理といった基盤業務も担当するなど、日々幅広い業務に向き合っています。
――どんな時に、やりがいを感じますか?
北爪)普段から、職員が困りごとを相談しやすい環境や雰囲気づくりを心がけています。だから、「声」を受け止めて改善策を提案し、業務がスムーズになったときは本当にうれしいです。
そうした個々の対応の積み重ねから、組織全体の課題が見えてくることもあります。組織内のビジョンの共有や部署間の相互理解促進が必要と考え、全職員が参加する研修会を企画・開催してきました。課題解決のため、組織の枠組みをどのように変えていけばよいのか。そのための企画から運用まで一貫して関わることができるのは、50人規模の組織だからできることであり、大きなやりがいを感じています。
また、多様な経験を持つ職員たちと働けることで、視野が広がり、学ぶことも多く、非常に良い刺激を受けます。総務部のメンバーは経歴も年齢もさまざまですが、フラットな関係性で、互いの意見を尊重した上で一緒にブラッシュアップできる環境です。
――JSCPに入る前は、どんなことをしていましたか?

北爪)大学卒業後は、保険業界のシステムエンジニア(SE)として約7年間働きました。プログラミングによるシステム開発から始まり、プロジェクトリーダーとしてチームをまとめる経験も積みました。顧客の要望を聴き、システムを設計・開発・改善するプロセスは、課題を整理して解決策を形にする点で今の仕事と共通しています。SE時代に培ったプロジェクト管理の力は、総務の業務改善に大きく役立っていると感じています。
――自殺対策にかかわるきっかけは?
北爪)私自身、小学校時代にいじめに遭い、「死にたい」と思い続けてきた経験があります。当時は、「知られてはいけない」と思っていたので、誰にも言えないまま大人になりました。大学4年の5月に就職が決まった頃、自殺対策のNPO法人が学生インターンを募集していることをSNSで知り、応募しました。「死にたい」というのは私の個人的な問題だと思っていましたが、社会問題として捉え、本気で向き合っている大人がいることに衝撃を受けました。
就職後も社会人ボランティアとして自殺対策に関わりたいと思っていたものの、SEの仕事が忙しく、遠のいていました。しかし30歳を前に、本当に大切だと思うことに時間を使いたいと考え、転職を決意しました。2020年2月からJSCPの立ち上げ準備に携わり、4月に職員となりました。
――今後、取り組みたいことは?
北爪) JSCPの事業は年々広がり、外部との連携も増えています。そうした中で、外部の関係者も含め自殺対策に関わる全員が自己の経験と能力を最大限に発揮できるよう環境を整えることに、今後も力を注いでいきたいです。
一方で、こどもの自殺が過去最多となる中で、過去の私のように苦しんでいるこどもたちが少しでも生きやすくなるよう、「自分にも何かできないだろうか」という思いがあります。そのため、JSCPの有志メンバーによる「いのち支える動画コンテスト」や「#逃げ活」といったこども・若者向けの啓発プロジェクトにも参加しています。
小学生のころから常に私の中にあった「死にたい」という気持ちは、気づけば、今はほとんどなくなっています。インターンや職員として自殺対策に携わる中で、自分に嘘をつかず安心して本音を語れる場に出会い、受け止めてもらえたことが大きかったのかもしれません。今度は私が、誰かにそうした安心感やプラスの影響を届けられる存在になりたいです。
■職員インタビューのバックナンバーは、こちら