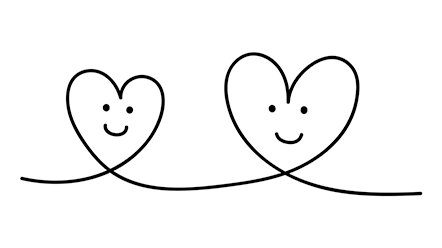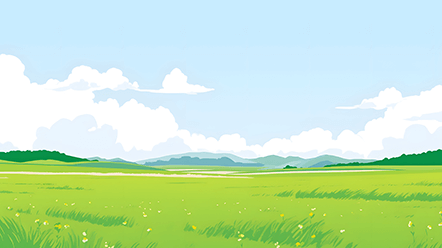SPECIAL


「死にたい」自分 肯定しよう 当事者の声聞き続けたテレビディレクターが伝えたいこと
Yahoo!ニュース個人で2022年8月16日に公開した記事を転載しています。
 「ももさんと7人のパパゲーノ」の一場面(NHK)
「ももさんと7人のパパゲーノ」の一場面(NHK)
NHKの特集ドラマ「ももさんと7人のパパゲーノ」が8月20日に放送される。これまで「死にたい」気持ちを隠して生きてきた主人公のもも(25)が、旅の途中で、それぞれに生きづらさと折り合う7人に出会い、「死にたい」自分を肯定していく物語だ。
ドラマの制作は、一般社団法人「いのち支える自殺対策推進センター」(JSCP)代表理事でもあるNPO法人「自殺対策支援センターライフリンク」の清水康之代表が自殺対策考証を務め、WHO(世界保健機関)が自殺に関する映像制作の留意点をまとめたガイドラインを参照して行われた。作品が「死にたい」気持ちを抱える人に望ましくない影響を与える「ウェルテル効果」を抑え、生きることを後押しする「パパゲーノ効果」を高める配慮や試みが随所に施されている。
企画・演出を担当したNHKディレクターの後藤怜亜さんは、福祉番組の取材で5年半にわたり「死にたい」気持ちを抱えた当事者約20人の声を聞き続けてきた。後藤さんに、「死にたい」気持ちを聞き続ける中で見えてきたことや、ドラマに込めた思い、制作で特に留意した点などについて聞いた。
|
特集ドラマ「ももさんと7人のパパゲーノ」NHK総合で8月20日23時~24時 【作】加藤拓也 【キャスト】主人公「もも」を伊藤沙莉、7人の「パパゲーノ」を山崎紘菜、染谷将太、中島セナ、平原テツ、野間口徹、浅野和之、池谷のぶえが演じる。 |
後藤さんのインタビューを紹介する前に、自殺報道をめぐる近年の動きを少し紹介したい。
WHOは、特に著名人の自殺をセンセーショナルに報じたり、手段・場所を詳述したりするような報道が受け手の自殺リスクを高める恐れがあるとして、メディア関係者向けの「自殺対策を推進するためにメディア関係者に知ってもらいたい基礎知識 2017年版」(いわゆる「WHO自殺報道ガイドライン」)を発行している。
日本ではコロナ禍の中で著名人の自殺が相次いだ2020年に顕著なウェルテル効果が見られ、JSCPは、メディア各社に対し厚生労働省と連名でWHO自殺報道ガイドラインに沿った報道を呼びかけたり、メディア関係者向けの勉強会を開催したりしてきた。最近は、メディア各社等の努力によりガイドラインが浸透しつつある。
一方、映像制作従事者向けのWHOガイドライン「自殺対策を推進するために映画制作者と舞台・映像関係者に知ってもらいたい基礎知識」はまだあまり知られておらず、今回のドラマでの使用は先進的な試みといえるだろう。
 オンラインでのインタビューに応じてくれた後藤怜亜さん(筆者撮影)
オンラインでのインタビューに応じてくれた後藤怜亜さん(筆者撮影)
長く苦しい夜を越えてきた方たちの言葉に助けられ
後藤さんは2010年にNHKに入局し、2016年から福祉番組「ハートネットTV」を担当している。
同年からNHKの掲示板「自殺と向き合う」の運営・管理や、「生きるためのテレビーあした、会社に行きたくないー」「#8月31日の夜に。」「わたしはパパゲーノ~死にたい、でも、生きてる人の物語~」などの制作に携わってきた。
―――生きづらさや自殺といったテーマにもともと関心があったのですか?
(後藤さん)2016年に「生きるためのテレビ」の担当になり取材を始めてみて、「自分と関係があるテーマ」だと感じるようになりました。これまで「死にたい」気持ちを口に出して語る人は周りにおらず、番組で語られる「死にたい」気持ちを抱えた当事者の方の声が自分の中にすんなりと入ってきて、気持ちが安らぐのを感じたんです。自分の中にもあるもやもやしたものを、言葉にしてくれていたからだと思います。
最初は、「死にたい」気持ちを抱えた方はどこか関わり方が難しいところがあるのではないか…? といった偏見が正直ありました。でも、すぐに杞憂だったと気づきました。長く苦しい夜を幾度も越えてきた方たちの言葉やその人なりの生き方に私自身が助けられ、自分の中で解決できないままになっていた問題がスーッと解決していくことがあり、心を動かされました。
「死にたい」口にできない空気 社会にはある
―――「死にたい」と口にできない空気が、この社会にはありますか?
(後藤さん)そう感じます。ドラマの主人公の「もも」は、「自分よりももっとつらい人がいる」と、「死にたい」気持ちを隠して生きていました。取材の中でも、「死にたい」という言葉を周囲に否定されることで、自分の中で「言ってはいけないこと」と規定してしまうことの苦しさを感じました。「死にたい」と言っていいし、「死にたい」と言いながら生きていくことは何ら間違った選択肢ではない。そのことを、ドラマをとおして伝えたいと思いました。
―――ドラマ制作にはどんな気持ちで臨みましたか?
(後藤さん)私は「死にたい」気持ちは肯定していますが、自殺を肯定したいわけではなく、誰にも死んでほしくないと思っています。ドラマ制作には、「死にたい」という言葉を否定しないことで自ら命を絶つ人を一人でも減らしたい、という気持ちで臨みました。その思いは、出演者やスタッフ全員で共有し同じ方向を向いて取り組むことができたと感じています。キャストのみなさんの、こうしたテーマに関わる緊張感と熱意をひしひしと感じる現場でした。
「死にたい」気持ち 肯定した先で見えた「豊かさ」
後藤さんの取材は、一度話を聞いておしまいではない。その後も続く「死にたい」気持ちを聞き、関係を積み重ねていく。
―――継続的な取材をとおして、見えてきたことは何ですか?
(後藤さん)「死にたい」気持ちを抱えた方は、年がら年中憂鬱な表情でつらそうに暮らしているわけではありません。気持ちが張りつめた日もあれば、友達とばか話をして笑う日も、腹を立てて愚痴る日もあり、気持ちは移ろっていきます。
5年前に出会った当時16歳だった女性は、「二十歳になるまでに絶対に死にたい」と言っていました。体調が安定せず外出すら難しかった彼女が、二十歳を迎えた日、一人でコンビニに出かけ、大好きなキャラクターとのコラボ商品である缶チューハイを買い、部屋に戻って大好きなアーティストの曲を聞きながら初めてお酒を飲み、「おつかれさま」と自分を労った。後日、そう私に話してくれました。
二十歳になっても生きているのは当たり前、と思うかもしれません。でも、彼女と私にとっては特別でありすごいこと。その思いを共有できたことがすごく「豊か」だと感じました。
彼女だけでなく交流を続ける複数の方が、毎日をその人なりのやり方で「生き延ばし」ていることを私に話してくれますが、多くの方は「死にたい」気持ちを周囲には言えずに生きているから、それを聞かせてもらっているのはおそらく私だけです。彼女たちが日々を「生き延ばし」ている方法や気持ちは、もしかしたら他の方が1日を生きる助けになるかもしれません。私が独り占めするにはあまりにもったいなく、ドラマをとおして多くの方に伝えたいと思いました。
(「死にたい」気持ちを抱えながらも「死ぬ」以外の選択をしている人の物語には、自殺を抑止する「パパゲーノ効果」があるとされており、WHOの映像制作ガイドラインでも「効果的な問題対処の方法を示している人物や物語を取り入れる」ことなどが推奨されている。)
「分からなさ」を受け入れる
ドラマの主人公「もも」の名は、NHKの掲示板「自殺と向き合う」への投稿で最も多く登場するニックネームだという。
―――ももには、特定のモデルがいるのですか?
(後藤さん)特定のモデルはおらず、ももが「死にたい」と思う理由は明確に描いていません。2017年に当時16歳だった女性を取材し、なぜ死にたいと思ったのか、3時間インタビューをし一緒に考えました。いろいろな話をしてくれましたが、最後まで彼女自身にも、明確な理由は分かりませんでした。「理由が分からないけど死にたい」ことを放送することには局内でも意見が分かれましたが、いざ放送してみると「彼女の話を聞いて、自分が抱えてきた気持ちが間違いではないと気づけた」といった反響が非常にたくさん寄せられました。
家族や友人に恵まれていて、理由も分からない。でも、死にたい。そういう方が実はたくさんいて、言葉にすると周囲から否定されるので気持ちを隠しながら生きているのだと思いました。「分からない」ものを描くのはチャレンジングなことですが、今回のドラマでももをそういう人物として描くことには意味があるのではないかと考えています。
―――理由がないのに「死にたい」と思う方が多くいると思います?
(後藤さん)取材を続けてきて、本当の意味で理由なく死にたいと思う方はいないのではないかと思っています。でも、死にたい理由は一つではく、複数の理由が複合的に絡み合っているので、全員が他の人に分かるように言葉にできるわけではありません。特に若い方にとっては簡単なことではないのではないでしょうか。
 「ももさんと7人のパパゲーノ」の一場面(NHK)
「ももさんと7人のパパゲーノ」の一場面(NHK)
WHOの映像制作ガイドラインを参照
ドラマの制作は、WHOの映像制作ガイドラインを参照して行われた。
―――特に留意したのは、どんな点でしたか?
(後藤さん)まず、NPO法人「ライフリンク」の清水代表に自殺対策考証を担っていただき、自傷行為の場面や、登場人物が「死にたい」と屋上に上るシーンの撮影方法などについて、直接的な描写を避けるなどの助言を受けました。
また、キャストや制作者が集まって台本を読む「本読み」の際に、映像制作ガイドラインについて説明し、映像が「死にたい」気持ちを抱える視聴者に与える影響について理解を深めていただきました。加えて、ドラマで精神科医療考証を担っていただいた精神科医の松本俊彦先生から、出演者のみなさんに今作品に参加するうえで知っておいてほしいこととしてメッセージをいただき、出演・制作する人自身もこのテーマから影響を受ける可能性があること、不安な気持ちになった際は些細なことでも相談してもらえる現場づくりに努めることを周知し、撮影に挑みました。
こうした作業を積み重ねる中で、キャストとスタッフ全員が同じ方向を向いて作品を作り上げることができました。